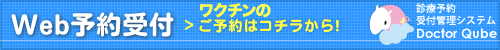予防接種について【2024.3 更新】
予防接種とは?
赤ちゃんや子どもは病気に対する抵抗力が未熟になります。生まれる前にお母さんからもらった免疫抗体も、生後半年程で弱くなってしまいます。
その後に特別な病気にかかってしまうと、重い後遺症や最悪いのちを奪われる可能性もあります。そうならないようにするために、予防接種があります。
予防接種は、対象となる疾患の偽物を注射して、その偽物と子どもが戦うことによって免疫抗体を獲得します。免疫抗体を獲得することで、本物の細菌やウイルスが体に侵入した際に戦うことができるようになります。
予防接種には「定期接種」と「任意接種」があります。しかし、任意接種の予防接種だからといって受ける必要がないわけではありません。 日本では違いますが、米国では、おたふくかぜ、インフルエンザなども定期接種になります。
どういう順序で受ければいいの?
スケジュール・接種間隔・同時接種については当院スタッフにご相談ください。
・NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会のサイトは非常に見やすいので参考になります。
・スマホで管理できる便利な無料アプリのダウンロードは、こちらになります。
・日本小児科学会の予防接種スケジュールのサイトも参考になるのでどうぞ。
・カラダノートのワクチンノートのアプリも見やすくておすすめです。
当院のおすすめ
⇒ 生後2ヶ月
・五種混合1期(1回目)※2024.4月から変更になりました。
・B型肝炎ワクチン(1回目)
・小児用肺炎球菌ワクチン(1回目)
・ロタウイルスワクチン(1回目) )
※当院のロタウイルスワクチンは「ロタリックス」全2回接種のものになります。
⇒ 生後3ヶ月
・五種混合ワクチン(1期)(2回目)※2024.4月から変更になりました。
・B型肝炎ワクチン(2回目)
・小児用肺炎球菌ワクチン(2回目)
・ロタウイルスワクチン(2回目)
⇒ 生後4ヶ月
・五種混合ワクチン(1期)(3回目)※2024.4月から変更になりました。
・小児用肺炎球菌ワクチン(3回目)
⇒ 生後5ヶ月
・BCGワクチン
⇒ 生後8ヶ月以降
・B型肝炎ワクチン(3回目)
・日本脳炎ワクチン(1期)(1回目)
・日本脳炎ワクチン(1期)(2回目)
※日本脳炎ワクチンの標準接種期間は3歳となっていますが、当院では3歳より前から接種を推奨しています。当院のワクチンスケジュールでは同時接種の観点から生後8ヶ月に記載してありますが、生後6カ月以降であれば接種可能です。(日本小児科学会も生後6ヶ月から接種を推奨しています)予診票が届いていないと思うので区役所で貰うか当院に置いてあります。
⇒ 1歳
・MR(麻疹・風疹混合)ワクチン(1回目)
・水痘ワクチン(1回目)
・おたふくかぜワクチン(1回目)【自費】
⇒ 1歳1ヶ月以降
・小児用肺炎球菌ワクチン(追加)(4回目)
・五種混合ワクチン(1期・追加)(4回目)※2024.4月から変更になりました。
⇒ 1歳3ヵ月以降
・水痘ワクチン(追加)(2回目)
⇒ 3歳以降
・おたふくかぜワクチン(2回目)【自費】
【まだ日本脳炎ワクチン受けていない場合】
・日本脳炎ワクチン(1期)(1回目)
・日本脳炎ワクチン(1期)(2回目)
⇒ 4歳以降
・日本脳炎ワクチン(1期・追加)(3回目)
※1期2回目から1年以上のあけば接種可能です。
⇒ 5歳になったら(年長)
・MR(麻疹・風疹混合)ワクチン(2回目)
・三種混合ワクチン+不活化ポリオワクチン(5回目)【自費】
※日本小児科学会では就学前に「三種混合(百日せきが含まれる)」と「不活化ポリオ」のワクチンを追加接種(5回目)することで、百日せきとポリオの免疫力を高めることを推奨しています。
⇒ 9歳頃
・日本脳炎ワクチン(2期)(4回目)
⇒ 11歳頃
・二種混合ワクチン
⇒ 12歳頃
・子宮頚がんワクチン3回接種(0か月・2か月後・6か月後)
⇒毎年秋頃
・インフルエンザワクチン【自費】
予防接種を受けた場合に注意することは?
予防接種当日であっても、お風呂に入って大丈夫です。
ただし、接種部位が強く腫れあがっている場合は、長風呂は避けましょう。
当日の注意事項
以下の場合は予防接種が受けられません。
・体温が 37.5°C以上である場合
・母子手帳を忘れた場合
・予診票を忘れた場合
予防接種の予約はこちらから